イノベーションで福島の地産地消の良さを再発見する


クリスティーナ・ジネル – 24/03/2023
2011年の原発事故以前は、日本有数の農業生産地であった福島。
しかし、現在では、福島県産の農産物を再び消費者に提供することができるようになりました。
生産者の熱意と除染作業(日本の当局によると、放射能濃度は大都市と同じレベルまで低下した)により、農業は再び徐々に発展しています。
鈴木酒造は12年ぶりに、震災で最も大きな被害を受けた地域のひとつである浪江の地に戻ってきた。
津波で流された古い酒蔵は、港の近くにあった。蔵人たちは漁師たちと密接な関係を持ち、大漁のお祝いにはその酒が振る舞われた。
浪江では、鈴木酒造の代表取締役である鈴木大介が、地元に希望と応援の気持ちを与えたいと考えています。
“震災前は120隻ほどあった漁船も、今は30隻を切っています。地元の漁業を支援するため、地元の人が食べる魚料理と私たちの酒の相性を測定し、AIと組み合わせて『魚酒マリアージュ』という酒を開発しました」とEuronewsに語っている。

日本酒は食べる米とは違う米を使って作るもので、土壌の除染が終わった後は、食用米の栽培が優先されました。そのため、大輔は技術革新に着手した。
“実際に食べているお米でお酒を作ったら、本当においしかった “と。しかも、浪江の米は変なところがないということを、日本酒を通じて広められると思ったんです」と明かした。
いわき市は「百聞は一見にしかず」。
この地域の農家や生産者は、消費者の悩みを解決するために、革新的な取り組みを行っています。
そのひとつが、いわき市にあるトマトのテーマパーク「ワンダーファーム」だ。 土を使わない最先端の生産システムとハウスを駆使し、震災後の増産に成功した元木洋さん。
消費者に農園を訪れてもらい、自分で収穫し、その品質を味わってもらうことで、トマトを使った地域活性化につなげています。
“地元を見て、野菜を収穫している生産者のことを知れば、野菜は安全だとお客さまに理解してもらえる。私の目的は、農業と観光の復興です」と、元木宏はユーロニュースの取材に答えた。

“農業だけでなく、レストランや農産物直売所、加工所も作ったのは、そのためです。人が来て楽しめるような施設を作りたい」と説明した。
農業体験やトマト料理を楽しんだり、トマト味噌やトマトアイスなどユニークな農産物を購入することができる。これらはすべて、元木さんの農場で作られている。

“震災後、結局、いろいろな人とつながったんです。
皆さん、福島の農産物に惚れ込んでくれました。
そして、「こんなにおいしくて、質のいいものが出荷できないなんて、もったいない」と、多くの人が思ってくれました。そして、「世界中に届けたい」と思ってくれたのです。
彼の農園は現在、地元の農家が新鮮な野菜を持ち帰り、販売したり、料理に使ったりする「農業地域拠点」になっている。
信じられない」: 福島の食材がシェフのお墨付きを得る
日本の首都・東京で、フランス人シェフのドミニク・コルビは、フレンチ・ジャパニーズ・レストランのオーナーを務めています。
彼はモトキのトマトを使い、2010年から福島の生産者との共同作業を始めた。

ちょうど震災の数日前、彼は現地視察に訪れていた。
震災のニュースがドミニクに衝撃を与え、それがきっかけで制作の復興やフォローアップに携わるようになった。
“ここは日本でも有数の富裕層が多い地域です。個人の豊かさだけでなく、農産物の豊かさにおいても。
100%安心して食べることができる。
農産物を販売するためのすべての工程を見たことがありますが、信じられないほどです。
だから、福島の産物は、本当の喜びと食への愛情をもって食べることができると思います」とドミニクは語った。
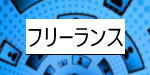


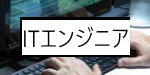

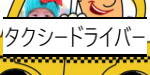
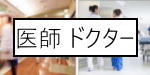
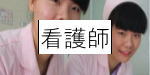
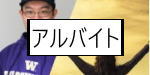
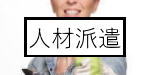
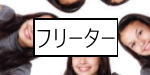
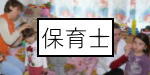


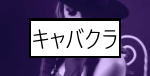
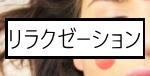

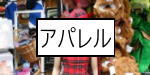


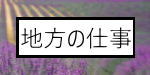
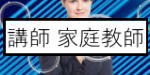
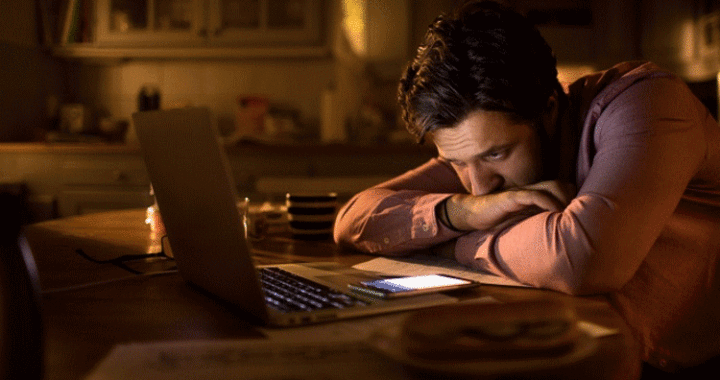 キャリアに行き詰まりを感じているあなたへ。どうすれば同僚と関係を築き、昇進できるでしょうか?
キャリアに行き詰まりを感じているあなたへ。どうすれば同僚と関係を築き、昇進できるでしょうか?  何をするにしても健康いちばん!良い仕事をするために免疫力を高めよう!
何をするにしても健康いちばん!良い仕事をするために免疫力を高めよう! 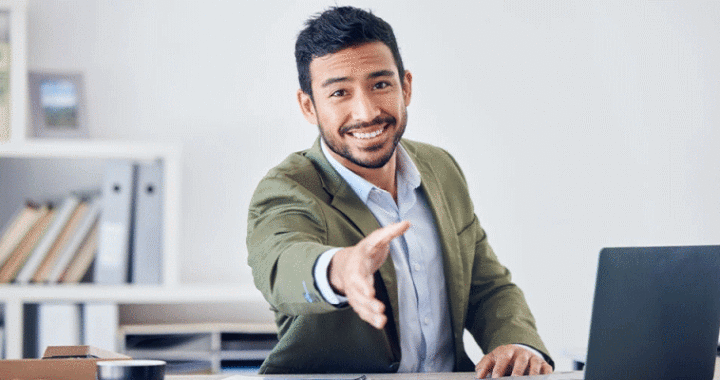 新入社員のみなさんへ、新しい仕事を成功させるための9つの方法
新入社員のみなさんへ、新しい仕事を成功させるための9つの方法  人権不安の中で移民協定はEUの「大きな」勝利として称賛される
人権不安の中で移民協定はEUの「大きな」勝利として称賛される